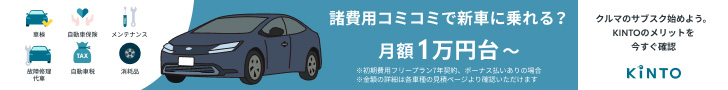この記事は昨年2022年1月6日にnoteに執筆したものを転載・編集したもので。
noteでは有料公開していましたが、1年すぎたので無料公開にしています。
合わせてこちらでもアーカイブで残していこうかと。
では本編スタートです。
前回のはこちら
1回目/2回目のあらすじ
1回目・2回目で
・2050年まではパリ協定の目標を軸に変化が起きる。
・規制を見越した各自動車メーカーの動き
・全体のパイが減っていく自動車業界の合理化の判断
・アメリカが混乱した理由
などを書いていきました。
よろしければ上記2点をよんでいただければ深掘りできるかと。
知っておこう。パリ協定の範囲、決まった時期。

温暖化問題の取り組みの軸はパリ協定ですが、
これは自動車業界だけでなく全てのものが対象で進んでいます。
つまり、インフラやエネルギー政策なども絡んでおり、
結果、風力発電や太陽光発電へのシフト、そして各企業の対応も含まれています。
つまり、「全部」です。
この「全部」が対象のこの取り組みに対し、「ハイブリットをつくれなかった欧州が日本車潰しのために電気自動車シフトをしている」なんて言えますかね?
まぁ、言うてる人がいるんですが、如何にこれらが視野の狭い考えか?
とってもわかると思います。
パリ協定の目標、「2050年にカーボンニュートラル 」に対する議論もぶっちゃけ不要です。
これらは「気候変動に関する法的拘束力のある国際条約」で、既にの目標でも対策としては遅すぎると言われています。
それに今頃チャチャ入れるのは遅すぎですよね。
簡単に書くとルールを作る場でルールを作る側に居るときにそれらは考えることです。
決まったことを後からごちゃごちゃ言うのは「偉い人が集まって決めた会社の決めごと」を後からルール変更しようとしているわけで、普通は無理ですよね。
え?その偉い人の考えがダメって?
「それはあなたの考えですよね」で済まされそうな思考かと。
そもそも2016年に発効されたパリ協定。
今は2022年。 注)執筆時は2022年でした。
6年も何をしていた?・・と突っ込まれるような話。
現時点でそれらで騒ぎ出したのであれば、6年間 問題視していなかったということなので、その環境意識のほうを問題にすべきだと思われ。
ということで、それら取り組みに対し、
「こうならばさらに環境負荷削減」や「このほうがエコロジーかつ効率的!」・・という議論はいいと思いますが、「これは無駄」「意味がない」といった考え方は生産性がなく進歩がないので好ましくないですよね。
評価はしても批判はいらん・・と思います。
もちろん評価のあとは改善ですよね。
それがいろいろ良い方向に進んでいくことだと思います。
と、いうことでそれらの世界の動きに対し、日本自動車メーカーがどう動いたか?・・を書いていきましょう。
パリ協定に対しての日本自動車メーカーの動き(1)
さて、日本自動車メーカーもパリ協定の動きを無視するわけにはいきません。
なにせグローバルな商売ですからね。
乗用車メーカーはスズキ・スバル・ダイハツ・トヨタ・日産・ホンダ・マツダ・三菱。
一つの国にこれだけメーカーがあると言うのも凄いと言えるわけですが、グローバル展開しているので提携関係を見ると意外と単体で動きが判断できないのがこの業界。
まずは提携がどうなっているか?・・を理解しましょう。
たとえばトヨタの場合、トヨタアライアンスがあります。
トヨタ(完全子会社:ダイハツ)
<提携>
スズキ(トヨタからの出資約5%・トヨタへの出資約1%未満)
マツダ(トヨタからの出資約5%・トヨタへの出資約0.2%未満)
スバル(トヨタからの出資約20%超・トヨタへの出資約1%未満)
スバルは20%なので、トヨタの「そのほかの関係会社」になっています。 そしてスバルの筆頭株主はトヨタです。
日産・三菱はルノーと提携しています。
いわゆる日産・三菱・ルノー連合です。
ルノーとの提携関係ですが・・
日産(ルノーからの出資約43.4%・ルノーへの出資約15%未満) 注)2022年の執筆時点
そして日産と三菱は・・
三菱(日産からの出資約34%)
つまりルノーは日産に大きく食い込み、そして日産は三菱に大きく食い込んでいる・・という図ですね。
そしてホンダはGMと業務提携
出典:日刊工業新聞2020年1月8日
そのようなグループ分けができ、それぞれの動きは連動していることが殆どです。
日本の主戦場は北米です。ヨーロッパは・・
そして大事な大前提。
日本自動車メーカーの殆どの主戦場は北米です。
次いで中国となっています。
ヨーロッパ圏はそれらと比べると驚くほど少なく、ヨーロッパ全体の販売台数は日本の販売台数以下です。
結果的に日本自動車メーカーの優先度は・・
アメリカ≧中国>日本>ヨーロッパ圏>その他
・・ということになります。
注)中国は合弁会社で地消地産が目的となっていることと、資産の持ち出し制限があるので企業から見ると他の市場とは全く異なる価値観の場所となります。そもそも合弁。単体ではなく。
実はBEVの流れに対応できてそうなメーカーは・・
さて、話を戻します。
日産・三菱・ルノー連合はきっちりBEVを続けていたとも言えます。
目立ちはしていませんが実は意外にBEVシフトに備えていたのがルノーの動きから見て取れます。
ただ、強烈なシフト・・はまだ起きておらず、これからと言ったところ。
日産・三菱・ルノー連合はバッテリーなどの調達については協調していると予想されます。
そしてホンダ。
昨年の内燃機からの撤退が印象的だったと思いますが、地味にホンダeなどを出してます。
・・が、それでどうにかなるわけでなく。
そのホンダ、GMと共同開発をいろいろと進めています。
これは主にGMのグローバルEVプラットフォームをベースに北米向けモデルを展開していく・・と予想されていますが、これも北米市場が主戦場な日本自動車メーカーらしい考え方だと思います。
これで北米向けで時間を稼げれば、それ以外も整っていく・・と言えましょう。
日本国内の報道ではその背景まで語られることも少なく、結果的にトヨタ以外の動きがわかりづらいように思われますが、実態としてはトヨタアライアンス以外は「割と対応できている」状況になっています。
トヨタ アライアンス(トヨタ除く)の動きは?
ちなみにトヨタ アライアンスでもスバル以外はトヨタ系でなく独自志向のBEVになりつつあります。
マツダについてはMX-30を既に発売。
既に独自で取り組んでいます。
ただし、どうも先行きが不明。
何かのタイミングでトヨタ系BEVモデルを活用するかもしれませんね。
そもそもバッテリー供給問題を抱えてそうです。
注)MX-30のロータリーレンジエクステンダーは2035年問題の解決策には実はなっていません。
スズキは独自でBEVを開発するような話が出ています。
見方によっては「トヨタのBEV待ち」だったわけですが、とある時に独自開発を感じさせる発表がありました。
2025年までに100万円台の軽BEVという話題がそれです。
これがトヨタ系のものかどうかは今後発売されるであろうダイハツのBEVとの比較で判明するわけですが、ダイハツのBEVの話題から察するにそれはないであろう・・と考察します。
さらば水平対向エンジン
ちなみにスバルについてはトヨタの出資比率が20%、そして筆頭株主ですから、今後はトヨタのOEMモデルが出てくるパターンになるのでは?・・と考察。
つまり、内燃機は引っ張れるだけ引っ張り、BEVに完全移行・・が考えらます。
bZ4X改めソルテラを踏み台にして自社BEV開発・・となれば期待したいところですが、現時点ではそれは無いと思われ。
それよりもソルテラのラインをスバル工場に作り、bZ4Xもそこで製造させてしまおう・・くらいトヨタは考えてそうな気がします。
そのような動きとなっていますが、何もパリ協定の取り組み開始の段階で確実に間に合っているとも言えず、今後の展開を急ぐ必要が出てくるであろうと思われます。
次回予告:トヨタの動きと日本メーカーの動きが鈍かった理由の考察
次回はこれらの動きに対するトヨタの動きの説明、
そして日本自動車メーカーが遅れていると言われる状態になった「欧州メーカーとの市場の違い」・・を書きたいと思います。
次回もよろしくおねがいします。
エックスサーバーを
お得に利用開始できる紹介URLを共有します。
以下のURLからのお申込みで、
初回のお支払い料金が最大10,000円OFFになる特典を
受けることができます!— 欧米気分を味わう方法/ブロガー&フリーモータージャーナリスト/abeo工房(公式) (@abeo_koubou) May 8, 2023
https://www.xserver.ne.jp/?referral_token=19167911096458b3191c505
お時間あるときにぜひどうぞ。noteも書いてます。